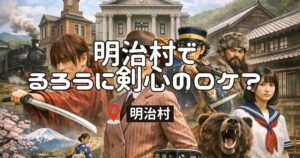犬山城って「誰が建てた」のか気になるけど、意外と知られていませんよね。
この記事では犬山城は誰が建てた?という疑問に答えつつ、歴史や見どころをまとめています。知れば旅の楽しみがぐっと深まりますよ。だから、気軽に読んでみてくださいね。
- 「犬山城は誰が建てた?」という築城の経緯と人物について
- 犬山城の歴史と戦国時代における役割の解説
- 信長との関わりや「白帝城」と呼ばれる由来の紹介
- 国宝に指定された理由と観光での見どころまとめ
犬山城は誰が建てた?築城者とその時代背景

犬山城は国宝に指定された日本最古の天守を持ち、その築城の経緯や戦国史との関わりを知ることで歴史的価値が鮮明になります。
誰が建てたのかを軸に、時代背景や別名の由来まで掘り下げていきましょう。
- 誰が建てた?建てた人と築城の経緯
- 犬山城の歴史と戦国時代の役割
- 織田信長との意外な関わりとは?
- 犬山城という名前の由来と呼ばれ方の変遷
- 図面は?
- 白帝城とは?
誰が建てた?建てた人と築城の経緯
犬山城は、1537年(天文6年)に織田信長の叔父である 織田信康(おだ のぶやす) が、かつての居城「木之下城」(きのしたじょう)から現在の場所へ移して築いた城です。
木曽川沿いの小高い丘は、交通と経済の要所として戦国時代にとても重要な場所だったため、城を築くにはぴったりでした 。
▼誰が作ったのかについて詳しくは以下の記事をご覧ください!
犬山城は誰が作った?築城の歴史と成り立ちをわかりやすく解説
犬山城の歴史と戦国時代の役割
犬山城は尾張国(現在の愛知県)と美濃国(現在の岐阜県)の境にあって、戦国時代を通じてとても重要な場所でした。この城は、領地争いや戦いのなかで何度も舞台となり、武将たちにとって大きな戦略拠点でした。
- 戦場としての要所
犬山城は木曽川沿いの小高い山に建っていて、尾張と美濃への交通がかたどられる場所にありました。そのため、戦国時代の戦いでは重要な拠点になっていました。 - 天下を狙う武将たちとの関わり
室町末期から戦国時代の終わりにかけて、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康という“三英傑”と呼ばれる武将たちが、この犬山城を手に入れようとして激しく争いました 。 - 小牧・長久手の戦いの前線にも
特に1584年の小牧・長久手の戦いでは、犬山城周辺が戦場の前線となり、両陣営のにらみ合いが続きました。
犬山城は、地理的な優位性と歴史に名高い武将たちの関係性から、戦国時代においてなくてはならなかった戦略拠点だったのです。
織田信長との意外な関わりとは?
犬山城は最初、信長の叔父・織田信康(おだ のぶやす)によって築かれましたが、意外なことに、その後、信長自身やその一族・家臣たちがこの城に深くかかわるようになります。
最初は信長と仲の良かった信康の子・織田信清が城主になりましたが、1564年(永禄8年)、信長に攻められて犬山城を奪われてしまいました。
その後、信長は城を家臣に与え、やがて自分の息子や乳兄弟、さらに豊臣秀吉、徳川家康など、有力な武将が城主をつとめるようになり、天下統一に向けた重要な拠点となっていったのです。
つまり、築城者の身内との関係や攻城戦、その後の城主の変遷を通じて、織田信長との関わりが予想以上に深いという点が、犬山城ならではの歴史的な面白さです。
犬山城という名前の由来と呼ばれ方の変遷
「犬山城」の名前は、城がある地名「犬山」からきています。
犬山という地名そのものには諸説あり、例えば「犬を使った狩りに適した土地だった」「小野山という名前が訛っていぬやまになった」「大縣(おおがた)神社のある方向が『戌亥(いぬい)』で、そこから犬山になった」などがあります 。
図面は?
犬山城では、古くからの絵図(古絵図)が残っていて、昔の城の形を知る重要な手がかりになっています。

寛文期(1680年代後半頃)に作られた「犬山城絵図」は、石垣の修復を幕府に申し出る際に描かれた控え図で、天守や櫓(やぐら)が立体的に描かれており、当時の構造がよく分かります。

また、1647年(正保4年)の絵図(「正保城絵図」)は、城内の曲輪配置などが詳細に描かれており、どこにどんな建物や石垣があったのかを確認できます。
他にも、曲輪(くるわ=城の区画のようなもの)の位置や本丸・二の丸・三の丸などの構成が、後世に控え図として手描きで残されている資料もあり、それらを元に城の全体像が分かるようになっています。
白帝城とは?
犬山城が「白帝城」とも呼ばれるのは、中国の詩に読みかけたある城の情景が重なるからです。
江戸時代の有名な儒学者・荻生徂徠(おぎゅうそらい)が、中国・長江のほとりにある「白帝城(はくていじょう)」を描いた李白(りはく)の詩、『早発白帝城(そうはつはくていじょう)』を思い出し、木曽川沿いにそびえる犬山城をその詩的なイメージになぞらえて「白帝城」と名づけたと伝えられています 。
特に、詩の中にある「朝焼けの雲に包まれた風景」や「川沿いの高台に立つ佇まい」が、犬山城の景観と重なって見えることから、荻生徂徠はこの詩句になぞらえて命名したのが由来です。
犬山城は誰が建てたのかを踏まえた現在の姿と豆知識
築城の歴史を理解した上で、現代の犬山城を知ることで、その文化的価値や観光スポットとしての魅力がより深まります。
管理体制や豆知識、観光情報を整理しました。
- 城主は現在誰?
- 持ち主の成瀬敦子は病気?
- 犬山城豆知識|国宝指定や見どころまとめ
- よくある質問|アクセス・入場料・見学時間
城主は現在誰?
犬山城(天守)は、2004年(平成16年)まで成瀬家による個人所有で維持されていましたが、その後、公益財団法人犬山城白帝文庫が設立され、現在はこの財団が所有・管理を行っています。
経緯を簡単に整理すると
2004年4月1日、成瀬家当主(第13代当主・成瀬淳子氏)が財団法人「犬山城白帝文庫」を設立し、犬山城の所有権を個人から法人に移しました。
設立された財団は、公益財団法人として継続して運営されており、現在も犬山城天守の所有者は「公益財団法人犬山城白帝文庫」です。
財団代表(理事長)は、成瀬家出身の成瀬淳子氏が務めています。
▼犬山城の所有について詳しくは以下の記事をご覧ください!
犬山城は個人所有?固定資産税はどうなる?相続税 評価額との関係や課税対象も解説
持ち主の成瀬敦子は病気?
成瀬淳子さんは、犬山城を個人所有から公益法人(犬山城白帝文庫)へ移すために奔走した方ですが、公の情報では「病気である」という記録や報道は確認できません。
成瀬淳子さんは第13代犬山城主として2004年に財団を設立し、理事長に就任しました。以降、現在に至るまで城の保存と公開を続けています。
一方で、メディアや公式資料の中に「淳子さんが病気である」という内容は見当たらず、そうした情報は確認できませんでした。
犬山城豆知識|国宝指定や見どころまとめ
国宝に指定された歴史ある天守
犬山城の天守は、1935年(昭和10年)に旧国宝として指定され、1952年(昭和27年)には新制度のもとで正式に国宝に再指定されました。戦争や天災、廃城令を乗り越え現存する貴重な建物です。
現存する日本最古の木造天守
この天守は、現存する日本の木造天守の中でも特に古く、全国に現存する天守の中でも最も古い一つとして知られています。
自然と一体になった美しい眺望
標高約85メートルの城山に建ち、背後は木曽川の断崖。天守最上階にある回廊(廻り縁)からは、木曽川をはじめ、岐阜城や名古屋駅周辺まで見渡せる絶景が楽しめます。
風情を感じる城下町との調和
城を囲む城下町には古い商家や石畳の道が残り、ゆったりとした散策が楽しめます。近くには庭園や博物館、そして木曽川の鵜飼など、見どころが盛りだくさんです。
貴重な木造建築を五感で味わえる
屋内には当時の木材が多く残されており、足音や床の膨らみなど「当時の時間の流れ」を感じられる造りになっています。
犬山城が国宝に選ばれた理由をもっと詳しく知りたい方はこちら
▶ 犬山城が国宝の理由とは?なぜ日本最古の木造天守が選ばれたのかを徹底解説
よくある質問|アクセス・入場料・見学時間
- 犬山城へのアクセスはどうしたらいいですか?
-
名鉄「犬山駅」から西口を出て、徒歩で約20分。
または「犬山遊園駅」からも西口を出て歩いて約15分です。 - 入場料はいくらですか?
-
大人(高校生以上)は550円、小・中学生は110円です。
- 団体で行った場合、割引はありますか?
-
はい。30人以上で大人490円、小中学生90円。100人以上だと大人440円、小中学生80円。300人以上では更に割引があり、2人まで車いすの方と付き添いの方は無料です
まとめ 犬山城は誰が建てた?
ここまでの内容を簡単にまとめると、犬山城は築城の経緯から現在まで、多くの歴史が重なり合うお城だと改めて感じます。
初めて訪れたとき、川の向こうにそびえる姿を見て「こんな場所に建てた理由があるんだ」と心から納得したことを思い出しました。築城者や戦国武将の動きに触れると、お城がただの観光地ではなく、日本史の舞台そのものだと気づかされます。
ポイントを絞ると以下の通りです。
- 犬山城は1537年に織田信長の叔父・織田信康によって築かれた
- 戦国時代は織田・豊臣・徳川が奪い合った重要拠点だった
- 「犬山城」という名前の由来や「白帝城」の別名が残る
- 国宝に指定され、日本最古の木造天守の一つとして現存している
- 現在は公益財団法人が所有し、一般公開され多くの人に親しまれている
こうして見ていくと、犬山城は単なる建物ではなく、歴史・文化・景観が三位一体となった特別な存在です。旅行で訪れるだけでなく、その背景を少し知るだけでも、見える景色がぐっと変わりますよ。私自身も知識を得てから再訪したとき、天守からの眺めがいっそう輝いて見えました。
参照元